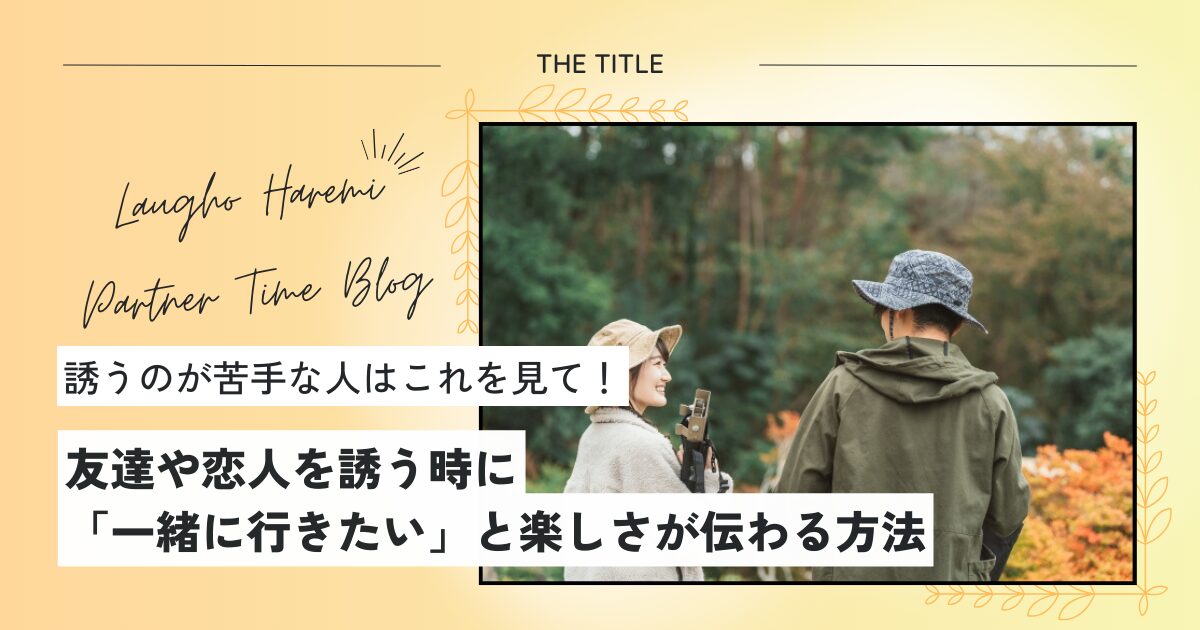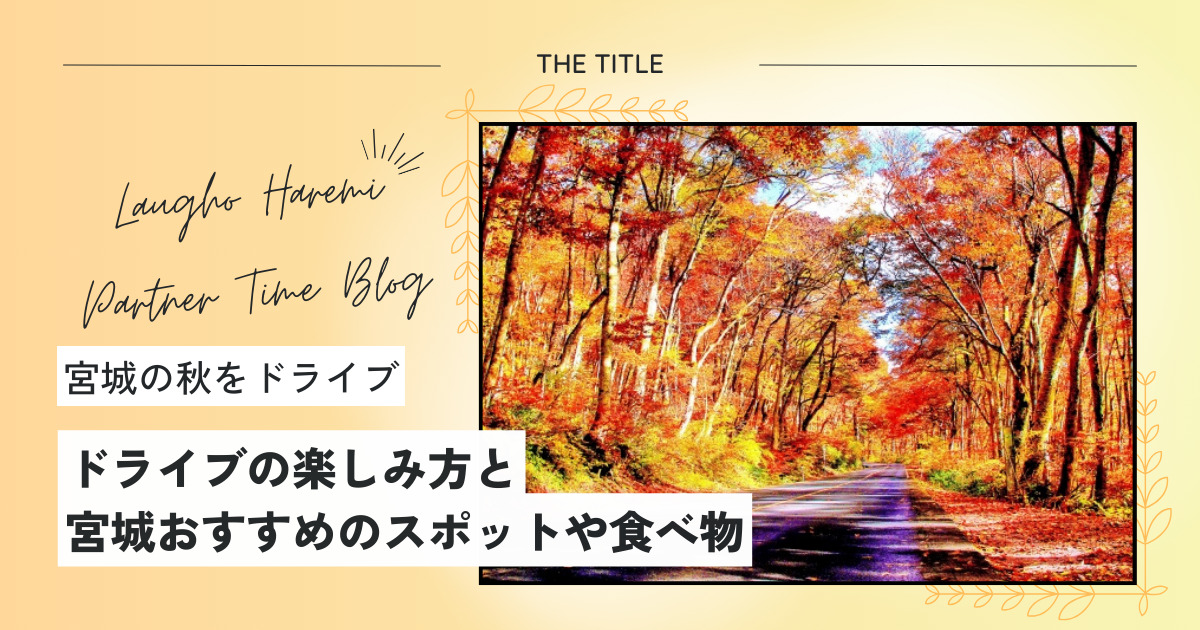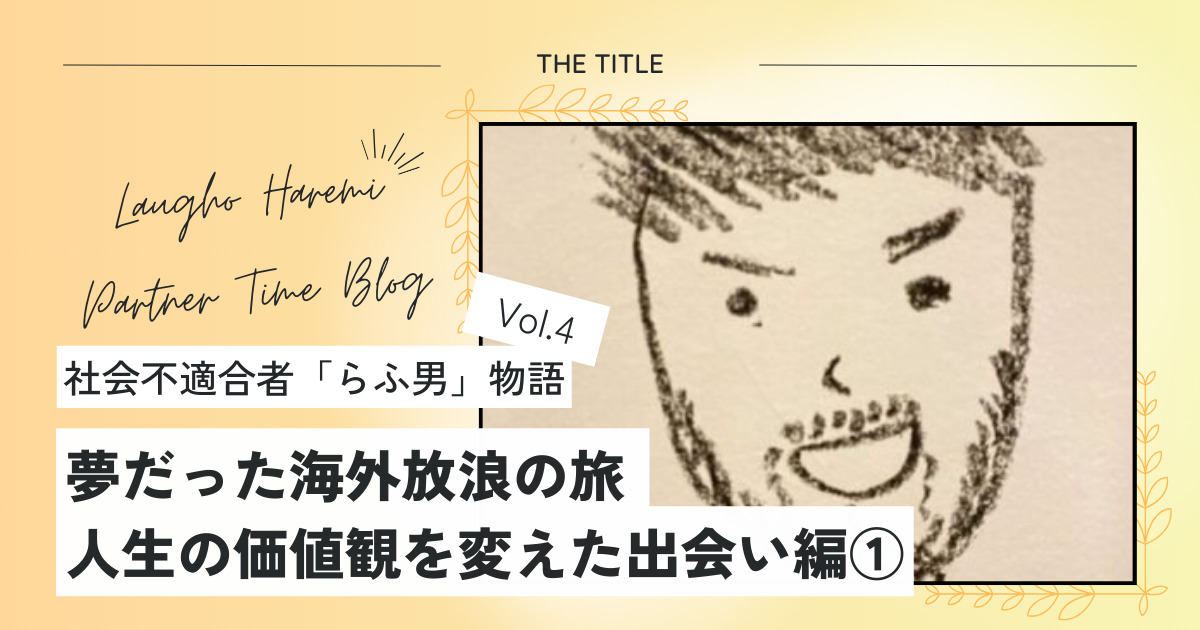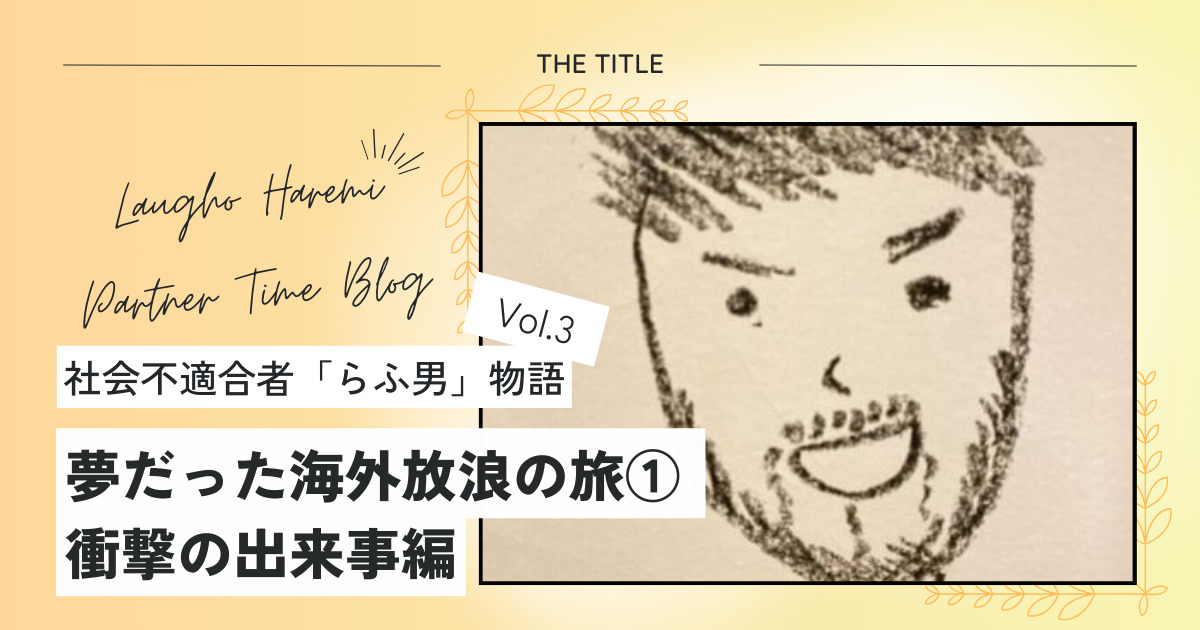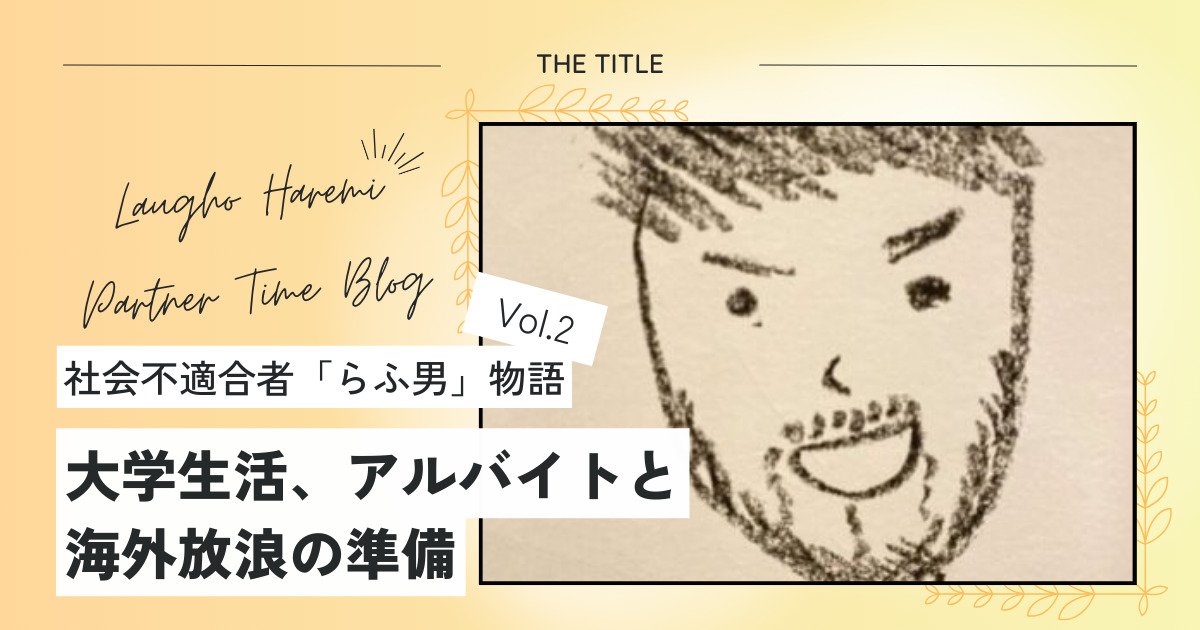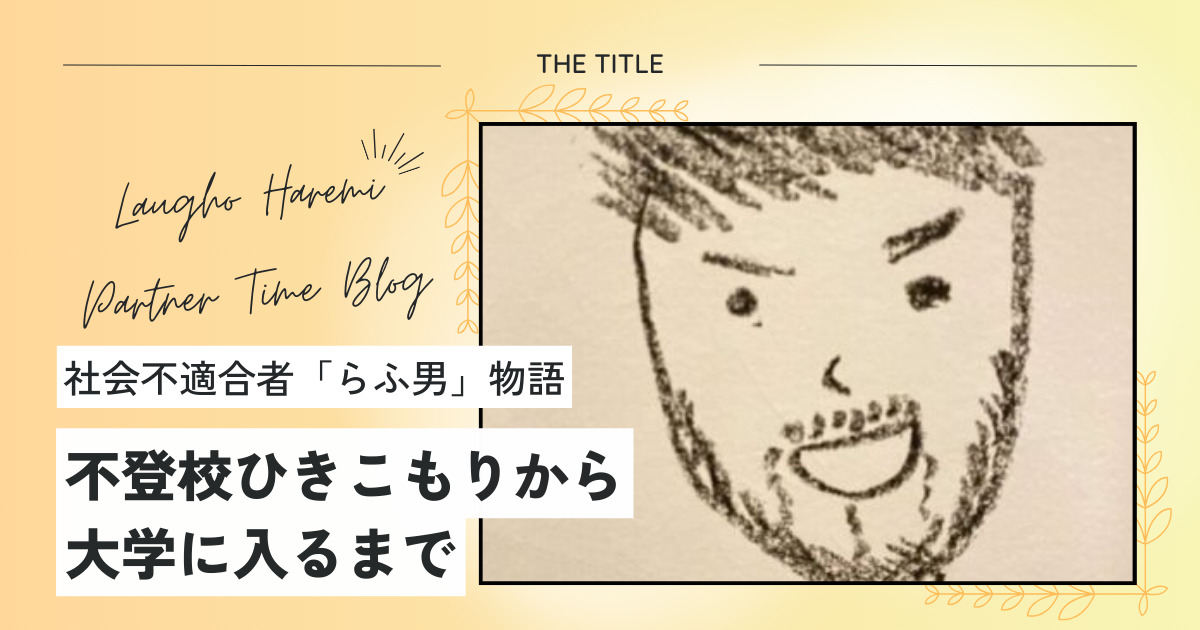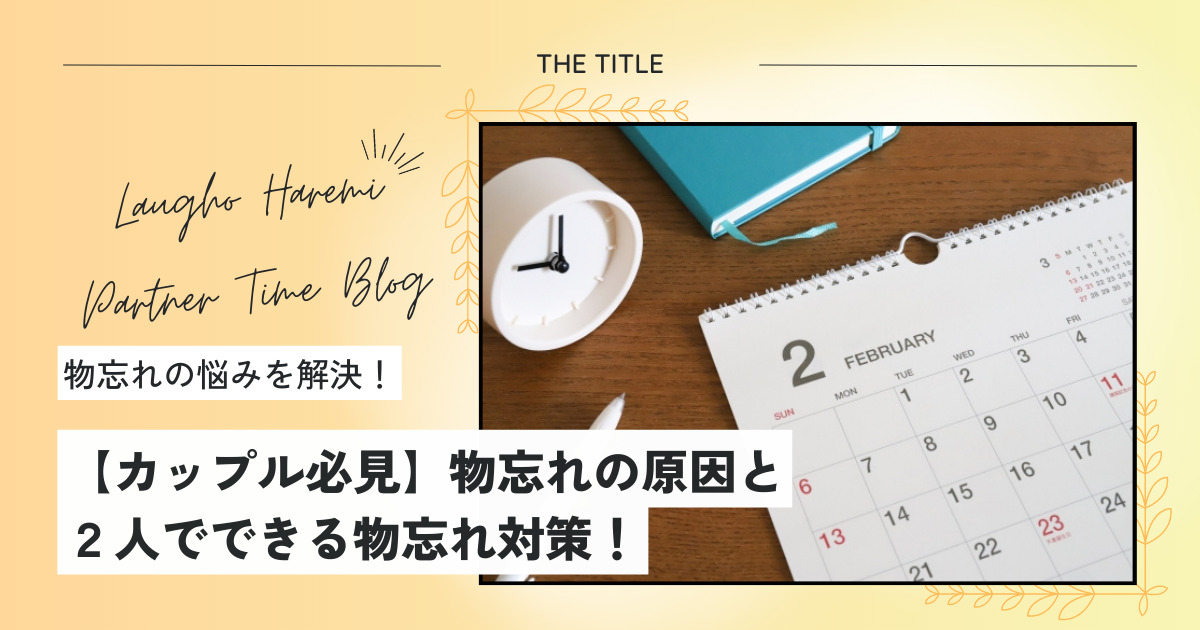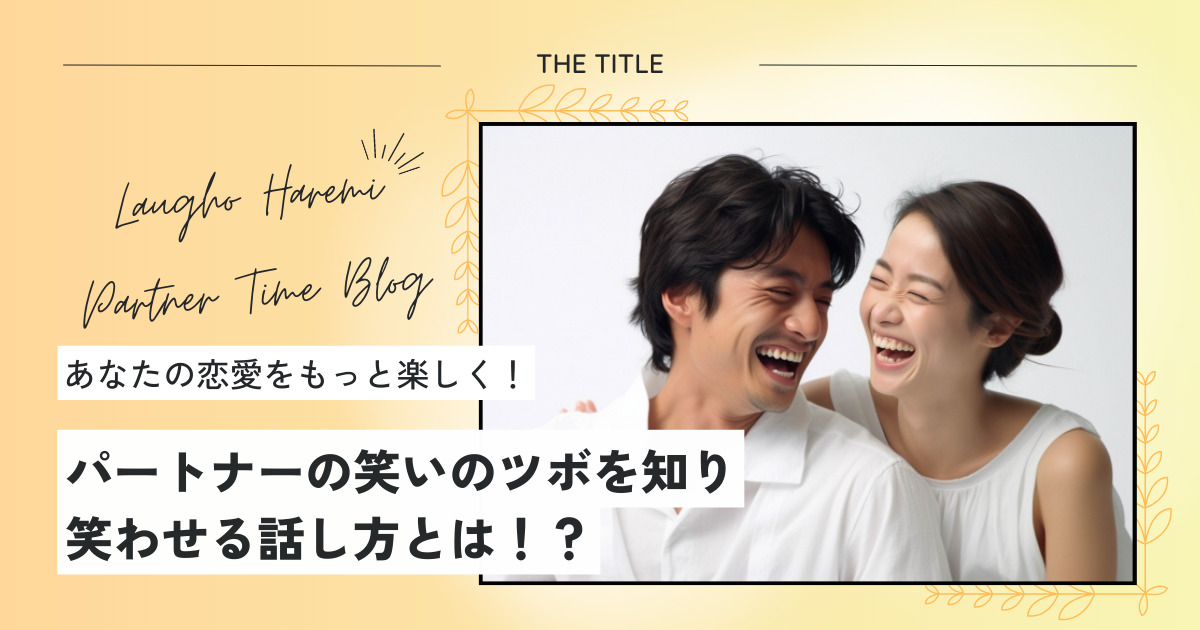らふ男はれ美
らふ男はれ美どうも! らふ男はれ美です!



ねーねーらふ男、ブログの書き方教えて!



(ざっくりだなw)えーっと投稿画面から新規作成で立ち上げて・・



そこじゃなくて、ブログの文章の書き方とかさ・・



文章の書き方?もっと具体的に言ってもらっても良い?



ん〜、具体的って言われてもわからない_| ̄|○
「教えて欲しいことがあるけど、どう質問したら良いんだろう・・・」と思ったことはありませんか?
質問の仕方次第で、相手は教えたいという気持ちになったり逆に教えたくなくなったりします。
この記事では相手に教えたいという気持ちにさせる質問の仕方や姿勢、返事の仕方について解説します。
- 質問の準備の仕方
- 質問をするときの姿勢
- 教えてもらう姿勢
- 継続して教えてもらうために大事なこと
教えたくなるような質問の仕方
まず質問したい内容をまとめて組み立てることと、言葉選びが大切です。
知りたいことに直結した言葉選びや質問の組み立て方法を解説します。
質問する前に、知りたい内容について自分で調べる


わからないことがあったときネットで検索することもありますね。
でもネットの情報だけではわからない・・・なんてこともあると思います。
自分なりに調べて、それでもわからないことをまとめておくことが大切です。
自分で何もせず、ただ質問をすると「なに言ってるの?」と相手に思われてしまい教えたくない気持ちになってしまうことがあります。
なのでまずは自分で調べて、なにがわからないのかをまとめましょう。
自分が知りたいことがまとまったら、質問を組み立てます。
質問を組み立てるときに「5W1H」という考え方があります。
「5W1H」とはWho(だれが)When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)の頭文字を取ってできた言葉で、具体的な質問をまとめることができるようになります。
クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンの使い分け
質問方法は、大きく分けるとクローズドクエスチョンとオープンクエスチョンというものがあります。
・クローズドクエスチョン:「はい」「いいえ」など簡潔な答えで済む質問 例:「あなたは〇〇が好きですか?」「どちらが良いと思いますか?」 ・オープンクエスチョン:自由な回答ができる質問 例:「あなたは〇〇について、どう考えていますか?」「〇〇したいのすが、どうしたら良いでしょうか?」
ざっくりまとめましたが、結局クローズドクエスチョンとオープンクエスチョンをどのくらいのバランスで使えば良いの?悩まれる方も多いと思います。
個人的にはオープンクエスチョンを多く使った方が相手の意見が聴けて勉強になるのでおすすめですが、使い方にはコツがあります。
ずばり、条件付けをすることです。
ここで先ほどの「5W1H」を使って組み立てた内容を活用すると自分の意図や目的が伝わり、ぐっと答えやすい質問になりますよ。
最後のまとめでオープンクエスチョンの上手な使い方の例を挙げているので参考にしてみてください。
決して、冒頭のようなざっくりした質問はしないでくださいね(笑)
質問をするときは言葉選びに注意
質問を組み立てたあとは、簡潔に伝えられる言葉選びをしてください。
例え知りたい内容が専門知識が必要な場合でも、誰でもわかる言葉を使うように心がけると相手も理解して答えやすいです。
もし教えてくれている人の返事や反応がいまいちだった場合は伝わっていない可能性があるので、わかりやすい言葉に言い換えたり質問内容が理解してもらえているかの確認も必要です。
自分が理解できているかも重要ですが、まずは相手に自分の質問を理解してもらうことを考えてください。
質問をするときの姿勢
質問をするときには、相手が教えたいという気持ちになるために言葉選びだけでなく姿勢も大切です。
教えてもらう謙虚な姿勢を意識して、好印象を与えられるようにしましょう。
質問をするときは相手に好印象を与える姿勢を意識しよう
質問をするときに以下のことに注意すると、相手に好感を与え教えたいという気持ちになってもらうことができます。
・顔の表情=目をはっきりと開く ・声のトーン=意欲のあるトーンで話せているか ・体の向き=相手の方を向いて話を聴く姿勢を取れているか ・目線=相手の目を見ているか
顔の表情や声のトーン、体の向き、目線は教えてもらう準備ができていますか?
うつむきがちで目も合わせず、ぼそぼそと話している人に教えたいと思いませんよね。
相手の立場に立ち、教えたいと思うような姿勢をイメージしてみてください。
相手に与える印象は、視覚情報が5割以上!?
直接会って話をするときに相手が受け取る印象は「視覚情報=55%、聴覚情報=38%、言語情報=7%」と言われています。ほぼ、視覚情報ですね。
相手が受け取る印象については、メラビアンの法則と呼ばれる心理学が参考になります。
こちらの記事に詳細があります↓


教えてもらっているときの姿勢・返事の仕方
教えてもらっているときに大切なことは、相手の話を聴く姿勢や返事です。
ちゃんと話を聴いて理解しようとする姿勢をしていると、教えたいという気持ちになってくれますよ。
話す以上に大切な聴く力|相手の話を理解する努力をしよう
教えてくれる人の話を聴くとき以下のことに注意すると、より理解が深まり相手に好感を与えます。
・他のことはせず相手の話に集中する ・話を聴いている最中は、適度な相槌をする ・相手の話をまとめて、理解できているか確認する ・忘れないように話の合間でメモを取る
逆に以下の行動は、相手に不快感を与えるので注意してください。
・スマホをいじったり他のことをしながら話を聴く ・話の途中で割り込んで意見を言う
適度に相槌を打ちながら聴くことで、教えてくれる人も話しやすくなります。
また話の合間では、メモを取ったり相手の話をまとめて理解できているかを確認することも大切です。
仮に確認をしなくて話し終えてから「理解できていなじゃん」となってしまっては、相手の労力が水の泡です。
相手が話しやすい聴き方と教えてくれた内容を理解する努力をすることで、教えたいという気持ちで話してもらうことができます。
教えてくれている相手に伝わるように返事をしよう
「はい」「なるほど」「そうなんですね」だけでは本当に理解して聴いているのかわかりませんよね。
教えてくれている人に理解できていることが伝わる返事をしましょう。
返事をするときには「なるほど、〇〇ということですね」「〇〇ということで合ってますか?」など相手の話をまとめた内容を付け加えて、理解できているのかを確認しましょう。
相手の話がわからないときには、わかったフリをせず素直に質問をすることも大切です。
返事とは、お互いに理解できているかの合図みたいなものです。相手に伝わるようこまめに返事をすると良いと思います。
そして最後には「ありがとう」という気持ちを言葉や行動で伝えると、教えてよかったという気持ちになってくれます。
継続して教えてもらうためには関係性が大事


そもそも教えたいという気持ちには、質問の仕方だけでなく教えてもらう人との関係性も影響します。
信頼関係を築き、お互いにギブアンドテイクできている関係性を目指してみてください。
継続して教えてもらうには、信頼関係を築こう
継続して教えてもらうためには「この人に教えてよかった」「今度また質問されたら丁寧に教えよう」と思ってもらえる信頼関係を築くことが大切です。
教えてもらったあとに以下のことをやると、信頼感を与えることができます。
・教えてもらったことは一通りやってみる ・進捗を伝える ・わからないことがあったら質問する
大事なのは「その場で聞いただけで終わり」ではなく、教えてもらったことを活かして行動すること。
教えてくれた人に対して進捗や結果を伝えることで安心感を与え、自分も教えてくれた人も達成感を味わうことができます。
わからないことがあれば素直に質問をして行動し続けていけば、信頼関係を築くことができますよ。
ギブアンドテイクの精神を持ち続ける
信頼関係を築くにはギブアンドテイク(Give and Take)の精神を持ち続けることが大事です。
ギブアンドテイク(Give and Take)とは、お互いに与え合う公平な関係性のことを言います。
教えてくれる人からすると自分が成長して貢献してくれることや、お礼を求めているのかもしれません。
つまり教えてもらったからには結果を出したり、お礼などの心遣いを忘れないことが継続して教えてもらえる秘訣なのですね。
「与えられるものなんてないよ・・・」と思ったとしても、教えてくれる人にとってどのようなギブ(Give)が嬉しいのかを想像して与え続けてみてください。
教えたくなる質問の仕方まとめ
普段、あなたがしている質問の仕方と比べてみてどうでしたか?
そこまで考えて質問してなかったという人が大半かと思います。(私もそうでしたw)
まとめると「質問の組み立てと言葉選び」「姿勢と返事の仕方」「教えてもらう人との関係性づくり」が大事です。
最初はうまくいかなかったとしても、やり続けていれば継続して教えてもらえるやり方が見つかるはずですよ。
日常の中でわからないことを質問をする機会はたくさんあります。
信頼関係を築いて、継続的に教えてもらえる人をつくるヒントになれば幸いです。



らふ男〜、〇〇をターゲットにこの商品を紹介する記事を書きたいんだけど、どう書き始めたら興味もってくれるかな?



なるほどね。それなら・・・こうした方が良いんじゃないかな。
(具体的で答えやすい!)



ありがとう!やってみるね
(やった!質問の内容が伝わった(*゚▽゚*))



SNSをフォローすると、新しい記事が出た時に通知がきますよ!